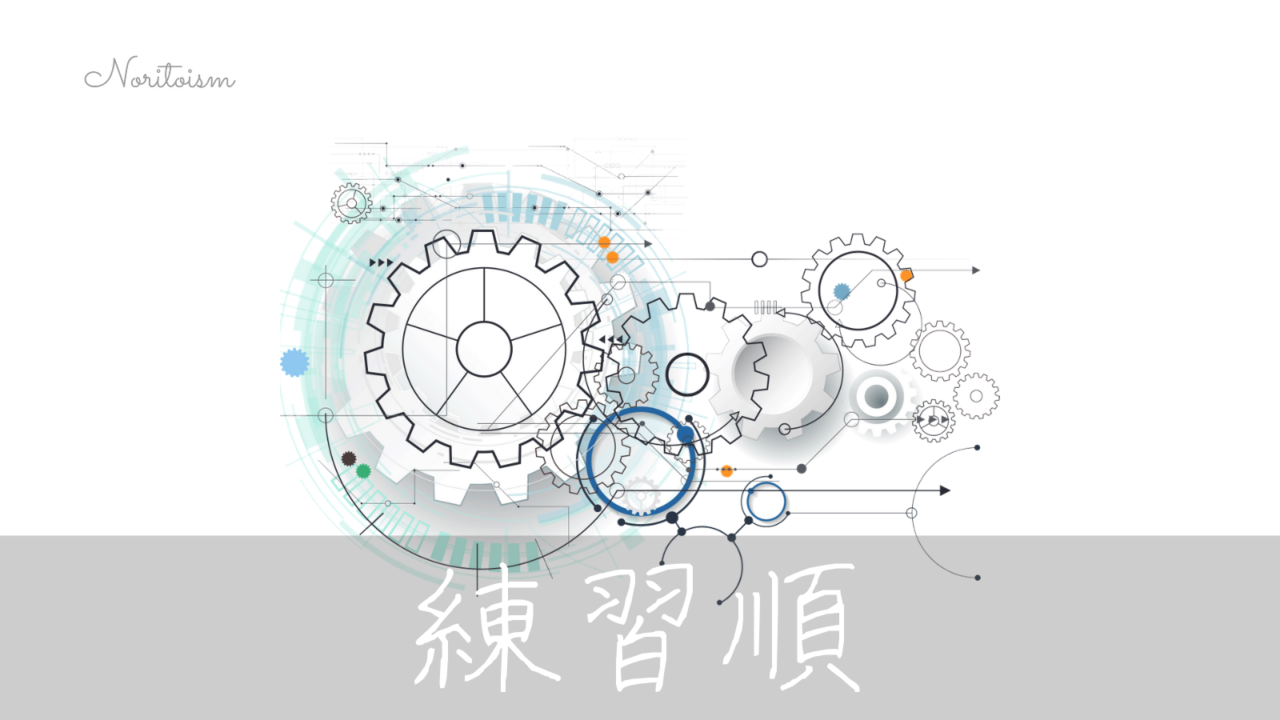やっぱ最初ってハノンからやるもんなの?
実は、そこで挫折する人、けっこう多いんだよね
有名だし、ちゃんとやっといた方がいいのかと思ってた
特に初心者だと、楽しさを感じる前にイヤになっちゃうことも多くて
この記事では、ハノンでつまずく理由と、
楽しく続けられる教本の選び方をわかりやすく紹介するよ
◆ 初心者が教本選びでよくある3つの間違い
◆ ハノンが合わない人のための代替案・練習法
◆ 教本選びで失敗しないための3つの視点
◆ Noritoismが考える“ピアノの入り口”とは

ピアノを始めたばかりの方にとって、「教本選び」は思った以上に大切なポイントです。
とくに“ハノン”は定番中の定番ですが、「なんだかつまらない…」「全然続かない…」と感じて、挫折してしまう人も少なくありません。
実はそれ、あなたの感覚が間違っているわけではなく、教本との“相性”が大きく影響しているんです。
この記事では、「なぜハノンでつまずきやすいのか?」という理由から、初心者がやりがちな教本選びの落とし穴、そしてモチベーションを保ちながら続けられる教材や選び方のコツまで、わかりやすくお伝えします。
「せっかく始めたピアノ、楽しく続けたい」と思っている方にこそ読んでほしい内容です。
教本との出会いが変われば、ピアノとの向き合い方もきっと変わります。
ハノンはなぜ初心者にとって“挫折ポイント”になりやすいのか
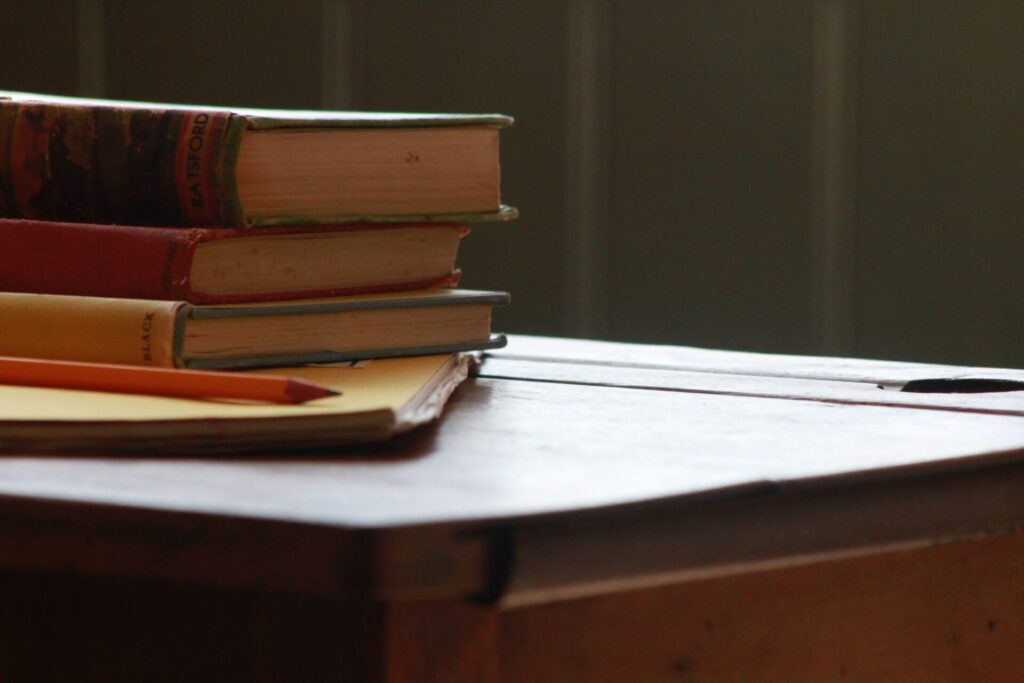
– 定番教本が“つまずきポイント”になる理由
「ただ指を動かすだけ」で音楽の楽しさを感じにくい
ハノンは、「指のトレーニング」に特化した教本です。
音階やパターンを繰り返し弾くことで、運指(指の動き)や脱力、リズム感を養う目的で作られています。
ただ、その内容は非常にシンプルで、メロディ性がほとんどありません。
「音楽を楽しむ」というより、「体を慣らす」ような印象を受けやすく、特に初心者にとっては退屈さや虚無感を感じやすい教材です。
「これって本当に音楽やってるのかな…?」と疑問に思ってしまうのも無理はありません。
成果が実感しづらく、飽きやすい構成
ハノンは「効果が出るまでに時間がかかる」タイプの教本です。
たとえば、以下のような違いがあります:
| 教本のタイプ | 練習内容 | 成果の実感度 | モチベーション維持 |
|---|---|---|---|
| ハノン | 指の独立・速さ | △ 遅め | × 飽きやすい |
| 曲集(例:ブルグミュラー) | メロディ・表現 | ◎ 感じやすい | ○ 続けやすい |
ハノンを毎日練習していても、「上手くなった!」と明確に感じるまでに時間がかかります。
目に見える成果がないと、人はなかなか続けられないもの。
特にピアノを始めたばかりの方にとっては、“上達の実感がない”ことが大きな壁になってしまうのです。
「音楽を感じる」体験が置き去りになる
多くの人がピアノを始めるきっかけは、「あの曲が弾けるようになりたい」「音楽を表現してみたい」といった感情や憧れからではないでしょうか。
でも、ハノンは“音楽的感動”とは対極にある内容です。
感情を込める余地がほとんどなく、機械的な反復運動に感じてしまうため、「楽しい!」よりも「修行っぽい…」という印象を持たれやすいのが現実です。
だからこそ、ハノンは“続けられる人を選ぶ”教材とも言えます。特に最初の教本として選ぶには、ややハードルが高いと言えるかもしれません。
初心者が教本選びでよくある3つの間違い

– モチベーションが続かない原因はここにある
有名=正解?定番に頼りすぎる選び方
ピアノ教本を選ぶとき、多くの人がまず検索したり、書店で「定番」とされるものを手に取りがちです。
もちろん、ハノンやバイエルなど歴史のある教本は、多くの指導者に支持されてきた実績があります。
ですが、「定番=誰にでも合う」ではないという点が、初心者が見落としやすいポイントです。
たとえば、運動が得意な人にとってはハノンのようなパターン練習が合っているかもしれませんが、表現や音の美しさを感じながら進めたい人にとっては、むしろ苦痛になってしまうこともあります。
大切なのは、「どんな教材か」だけでなく、「その人に合うかどうか」です。
レベル感が合わないと“やらされ感”に変わる
もうひとつありがちなのが、「少し難しすぎる教本」を選んでしまうことです。
とくに大人の独学者に多いのが、「子ども用の教材じゃ物足りないかな」と思って、つい背伸びした教本を選んでしまうパターン。
でも実は、難しすぎる教本はモチベーションを下げる最大の原因になります。
音が鳴らせても「なんか全然弾けてる気がしない…」という感覚が積み重なると、“楽しい”から“つらい”に変わってしまいがちです。
逆に、「簡単すぎるかも?」と思うくらいが、最初はちょうどいいケースも多いんです。
「順番通りにやるべき」という思い込みの落とし穴
教本には、たしかに順序立てて構成されているものが多くあります。
ですが、「1ページ目から順にすべてやらなければいけない」という思い込みは、練習の自由度を下げてしまう原因になります。
実際は、自分のペースや気分に合わせて“飛ばす”ことや“戻る”ことも大切です。
教本は“使いこなすもの”であって、“縛られるもの”ではありません。
「今日は好きな曲を練習して、明日はちょっと基礎をやってみよう」
そんな柔軟なスタンスで取り組めた方が、音楽との距離感も自然と心地よくなるはずです。
ハノンが合わない人のための代替案・練習法

– 続けたくなる教材は“楽しさ”から始まる
メロディで心が動く!ブルグミュラーやポピュラー曲集
もしハノンの無機質な練習に気が乗らないと感じたら、“メロディのある教材”に切り替えてみるのがおすすめです。
たとえば「ブルグミュラー25の練習曲」は、テクニックだけでなく物語性や情緒が感じられる名曲ぞろい。
「アラベスク」「貴婦人の乗馬」など、タイトルだけでワクワクするような曲が多く、“弾きたい気持ち”が自然と湧いてきます。
また、最近ではポピュラーソングやジブリ、ディズニーの初心者向けアレンジ楽譜も豊富です。
「この曲、聴いたことある!」という親しみやすさは、何よりのモチベーションになります。
悩んでる人 ピアノ始めたてでも弾ける楽譜なんてあるのかな? 知っている曲をすぐに弾けたら楽しいだろうな… Noritoism 初心者向けの楽譜はたくさん市販されてるよ! 曲を進めながら上達していく方もた[…]
感情と結びつく曲で音楽を体感する練習法
音楽は本来、「気持ちを表すための手段」です。
だからこそ、テクニックの前に「弾いていて心が動くこと」を大切にしたいところです。
たとえば:
- ゆったりした旋律で“静けさ”や“切なさ”を感じてみる
- 軽やかなリズムで“元気”や“楽しさ”を表現してみる
こうした体験は、どんな練習曲よりも深く、“音楽と自分がつながる感覚”を育ててくれます。
もちろん正確さや技巧も大切ですが、初心者のうちは「まず音楽を楽しむ」ことを最優先にしてOKです。
弾きたい曲から逆算して“目的別に選ぶ”
「どんな曲が弾けるようになりたいか?」を先にイメージしておくと、教本選びがぐっと楽になります。
たとえば:
| 目標のスタイル | 向いている教本・教材例 |
|---|---|
| クラシック曲を弾きたい | ツェルニー・ブルグミュラー・バッハの簡易版など |
| カフェ風BGMを弾きたい | ポピュラー曲集・Lofiピアノアレンジ本など |
| 自分で作曲・アレンジしたい | コード理論入門・即興ピアノ教材など |
目的が明確になることで、モチベーションも安定しますし、いま自分に必要な練習」が見えてくるので、無駄な遠回りをせずに済みます。
教本選びで失敗しないための3つの視点

– 長く続けられる教材の共通点とは?
「自分に合っているか」を最優先に考える
教本選びで一番大切なのは、「その教材が自分のペースに合っているか」という視点です。
- 読みやすい譜面か?
- 今の自分でも無理なく取り組めそうか?
- 説明や解説が理解しやすいか?
これらを判断するには、実際に数ページを立ち読みしたり、YouTubeなどで演奏例を見てみるのもおすすめです。
「これならできそう」「ちょっと弾いてみたいな」と思える感覚は、大きな続ける力になります。
他人のおすすめよりも、「自分がどう感じたか」を軸に選ぶことが、遠回りしない一番の近道です。
楽しく進められる=継続力につながる
ピアノを続けるには、“少しでも楽しい”と感じられる瞬間を積み重ねることが何より大切です。
どんなに効果的な練習でも、「楽しくない」と感じてしまえば、それは続けられません。
逆に、多少テクニック的に偏りがあっても、「楽しくて毎日触りたくなる教材」なら、自然と上達につながっていきます。
たとえば:
- 好きな曲の簡単アレンジ
- 弾いていて癒されるメロディ
- 難しすぎず、すこし背伸びできる内容
「できた!」という小さな達成感が、やがて大きな習慣になります。
楽譜を開くたびにワクワクできる教材を選びましょう。
信頼できる人のアドバイスを参考にする
独学の方にとっては特に、「どれを選べばいいのか正直よくわからない…」という悩みがつきものです。
そんなときは、信頼できる先生や経験者の声をうまく取り入れてみましょう。
ピアノ歴の長い人は、自分の失敗や遠回りの経験を踏まえて、「こういう人にはこの教材が向いてるよ」と具体的なアドバイスをくれることが多いです。
また、SNSやブログなどで「○○という教材で伸びた」「この本は合わなかった」などのリアルな体験談を参考にするのもひとつの方法です。
ただし、最後に決めるのは自分自身。
アドバイスは“参考材料”として活用しつつ、「自分にとって気持ちよく使えるか」を軸に選びましょう。
Noritoismが考える“ピアノの入り口”とは
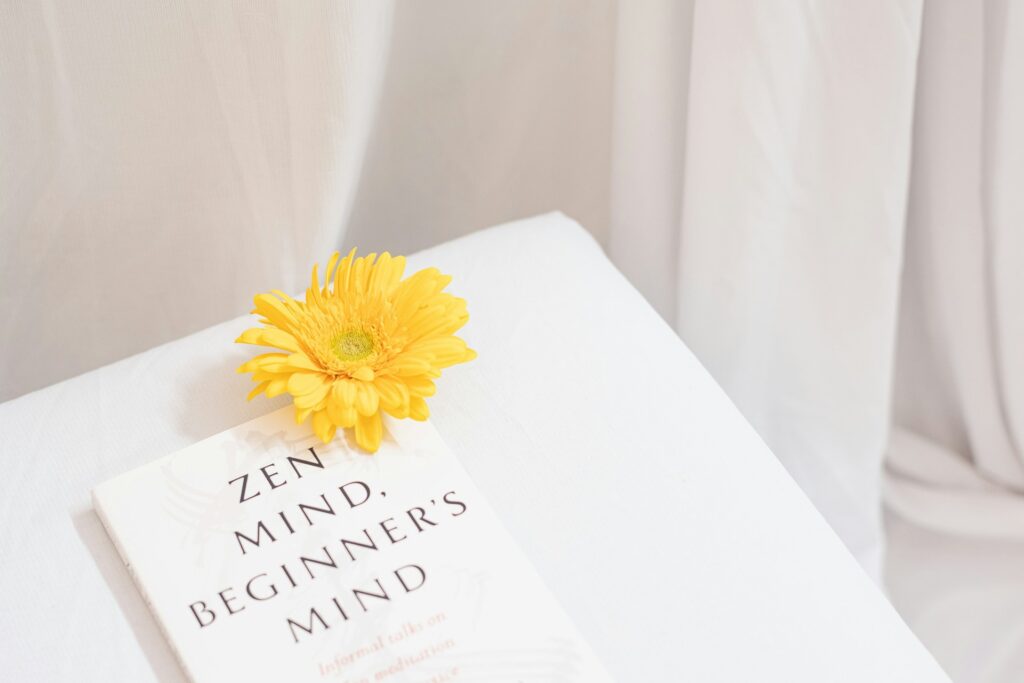
– 表現する喜びからスタートする、もう一つの入口
音楽との出会いに、正解や順番はいらない
ピアノを始めたとき、上達や技術よりも先に、「ただ弾いていて気持ちいい」と思えた瞬間はありませんか?
私は、音楽との出会いはもっと自由でいいと考えています。
誰かが決めた順番やカリキュラムに従うよりも、心が動いた曲、触れてみたい音に出会ったときこそ、本当のスタートだと思うのです。
それがクラシックでも、映画音楽でも、自分で作った小さなメロディでもかまいません。
“自分の中にある音”と自然につながる体験こそが、ピアノのいちばん素直な入り口です。
「音を楽しむこと」が、いちばん大切なテクニック
テクニックや練習ももちろん大切ですが、それはあくまで「音を楽しむ」ための手段です。
ノーミスで弾けなくても、テンポが不安定でも、そこに気持ちがこもっていれば、ちゃんと音楽になると私は信じています。
私自身、演奏や作曲を通していつも感じているのは、「美しい音」は、“正確な演奏”よりも“やさしい気持ち”や“静かな情景”の中から生まれる、ということ。
だから、最初のうちは「間違えないこと」よりも、「気持ちよく弾けること」を大切にしてほしいと思います。
小さな成功体験の積み重ねが、音楽との信頼になる
初心者のころは、「まだまだだな…」「もっと練習しなきゃ」と思うことが多いかもしれません。
でも、たとえ1小節でも「今日ちょっと弾けた!」と思えることが、音楽との信頼関係をつくってくれます。
自分の音が心に届く瞬間を、ひとつずつ積み重ねる。
それがきっと、ピアノを“生活の一部”として楽しめる一歩になるはずです。
そんな思いで、私は聴く人にも、演奏する人にもやさしい音楽を作り続けています。
もし、Noritoismの音があなたの“ピアノの入り口”になれたなら、それほど嬉しいことはありません。
ピアノ初心者が教本選びでつまずかないために大切なことまとめ
ハノンは「定番のピアノ教本」
ではあるものの、初心者にとっては“音楽の楽しさを感じにくい”“成果が見えにくい”といった理由から、挫折の原因になりやすい
教本選びでよくある失敗には、以下のような傾向がある
- 有名だからと選んでしまう
- レベルが合わずストレスに感じる
- 決められた順番にこだわりすぎる
「楽しい」「もっと弾きたい」
と思える教本を選ぶことで、ピアノとの距離が自然と近づき、継続もしやすくなる
ハノンが合わないと感じた人には、以下のような代替アプローチが効果的
- ブルグミュラーやポピュラー曲集など、メロディのある教材
- 感情とつながる曲で“音楽を体感”する練習法
- 弾きたい曲から逆算して教材を選ぶ方法
教本選びで失敗しないためには、以下の3つの視点を意識すること
- 自分の性格やペースに合っているか?
- 弾いていて楽しいと感じられるか?
- 信頼できる人のアドバイスを柔軟に取り入れる
最後に、Noritoismが考える“ピアノの入り口”は
技術や順番よりも「音楽と自分がつながる感覚」を大切にすること。
表現の喜びを知ることが、何よりも自然で、豊かなスタートになる
ピアノを学ぶ上で、教本は「進み方を決める地図」のような存在です。
だからこそ、その地図が自分に合っているかどうかをしっかり見極めることで、もっと自由に、もっと楽しく、音楽の世界を歩んでいけるはずです。
第5話、その他のピアノ練習法はこちらです。
悩んでる人 ピアノって練習が欠かせないよね。 どんな練習をしたら1番効果的なのかな? Noritoism ただ闇雲にピアノを弾き続ければいいわけじゃなくて、 正しい工夫でかなり効果的な練習が期待できるよ[…]