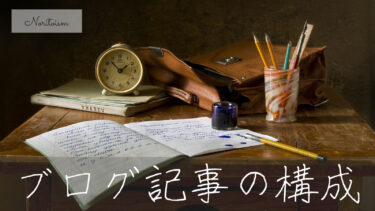もしかしてサイト構造って関係ある?
サイト構造って、検索エンジンにもユーザーにも
“わかりやすく伝える仕組み”みたいなものだからね。
何をどうすればいいの?
細かいけど、ちゃんと整えると検索順位も安定してくるんだよ。
基本から教えてもらえる?
6つの対策に分けてわかりやすく解説していくよ。
検索上位を狙いたい人には必須の内容だから、ぜひ最後までチェックしてみて!
◆ サイト構造を設計する前にやるべき3つの下準備
◆ SEOに強くなる!サイト構造の対策6選【基本から応用まで】
◆ 構造改善の効果を測定!チェックすべき指標とツール一覧
◆ やりがちな失敗とその対策Q&A|リダイレクト・タグ乱立など
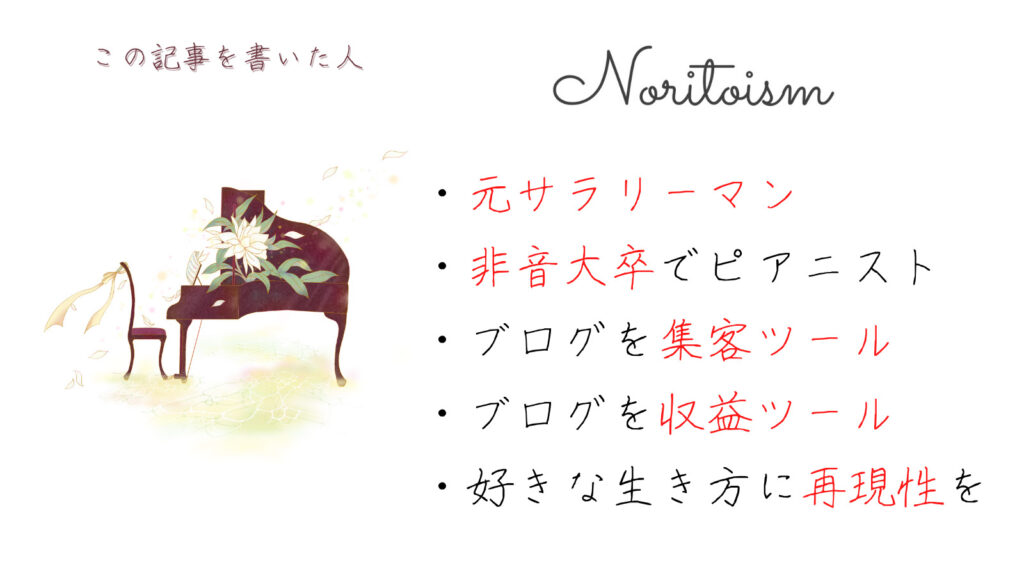
あなたのサイト、検索順位が伸び悩んでいませんか?
実はその原因、「サイト構造」にあるかもしれません。
いくら良いコンテンツを書いても、構造が整っていないと検索エンジンにもユーザーにも正しく評価されにくくなってしまいます。
でもご安心ください。この記事では、SEOに強くなるための「サイト構造の改善ポイント」を6つに厳選して、基本から実践テクニックまで丁寧に解説していきます。
具体的には、階層設計・内部リンク・パンくずリスト・サイトマップ・URLの最適化など、どれも検索順位や回遊率に直結する要素ばかり。
また、設計前の準備や効果測定の方法、ありがちな失敗パターンも合わせて紹介するので、初めての方でも安心して取り組める内容です。
検索上位を本気で目指すなら、「サイト構造」は絶対に避けて通れません。
ぜひこの機会に、あなたのサイトを根本から見直してみませんか?
SEOについて「?????」という方、自信がない方は、最初にこちらをご覧いただけると分かりやすいです。
悩んでる人 ブログからファンを作るために、SEO対策って何をしたらいいの? そもそも、SEO対策ってなぜするの? Noritoism SEO対策は一言でいうと「読者のためのブログを作る」 検索上位に表示[…]
- 1 なぜサイト構造がSEOに効くのか?今すぐ見直すべき理由
- 2 サイト構造を設計する前にやるべき3つの下準備
- 3 SEOに強くなる!サイト構造の対策6選【基本から応用まで】
- 4 構造改善の効果を測定!チェックすべき指標とツール一覧
- 5 やりがちな失敗とその対策Q&A|リダイレクト・タグ乱立など
- 6 まとめ|検索上位を狙うなら、サイト構造の最適化がカギ
なぜサイト構造がSEOに効くのか?今すぐ見直すべき理由
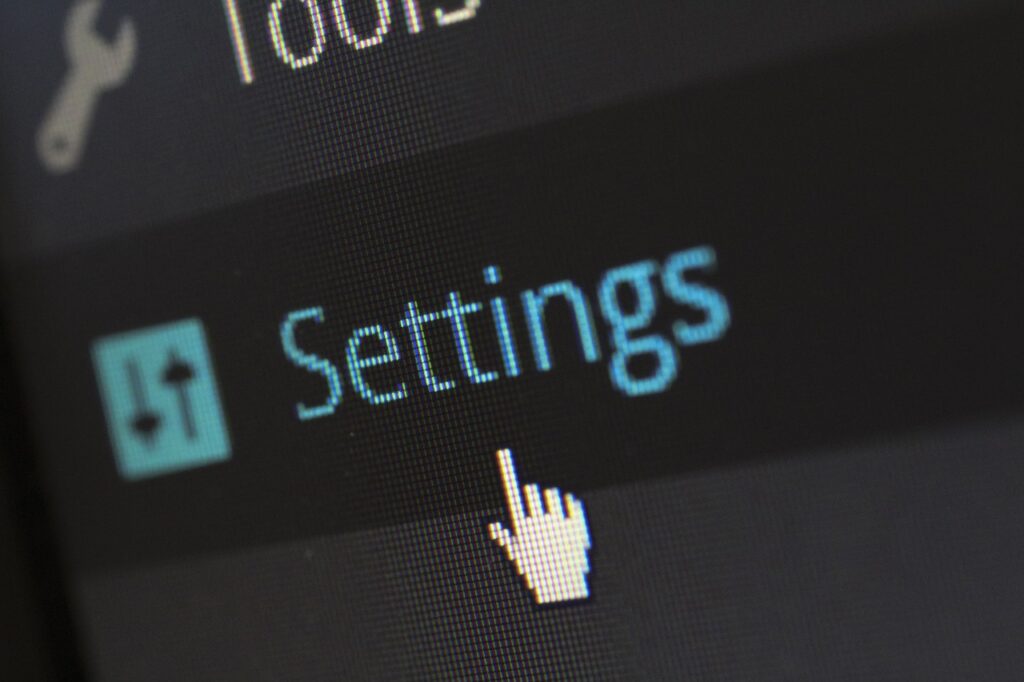
「コンテンツには力を入れてるのに、なんだか検索順位が上がらない…」
そんなときに見直したいのがサイト全体の“構造”です。
実は、検索エンジンがあなたのサイトをどのように理解し、評価するかは、構造次第で大きく左右されるのです。
ここでは、サイト構造がSEOに効く3つの代表的な理由をわかりやすくご紹介します。
クロール効率が上がると、インデックスが安定する
Googleのクローラー(検索エンジンの巡回ロボット)は、リンクをたどってページを見つけていきます。
そのため、構造が整理されていて内部リンクが適切に張られているサイトほど、効率よく巡回されるんです。
逆に、ページ同士のつながりが弱かったり、階層が深すぎたりすると、一部のページが見つけられずインデックスされないという事態も起こりえます。
🔍補足:インデックスされていないページは、検索結果に一切表示されません。
クロール効率を上げること=検索エンジンに見てもらえるチャンスを増やすこと。
その第一歩として、サイト構造の最適化は非常に重要です。
評価が伝わりやすくなり、重要ページが上位表示されやすくなる
SEOの世界では「内部リンク=評価の受け渡し」とも言われます。
サイト内の構造が整っていると、どのページが“重要”なのかが検索エンジンに明確に伝わりやすくなるのです。
たとえば、トップページから2クリック以内にアクセスできていて、さらに他のページからも多くリンクされているページは、「このサイトでは重要」と判断されやすくなります。
| 状況 | 評価の伝わりやすさ | 検索順位への好影響 |
|---|---|---|
| 他ページからリンクが集まる | ◎ とても良い | ◎ 期待できる |
| 深い階層にあり孤立している | ✕ 悪い | ✕ 出にくい |
「このページを上位表示させたい」という戦略があるなら、そのためのリンク設計や構造整理が欠かせません。
回遊性が高まり、ユーザー体験(UX)が向上する
ユーザーにとっても、わかりやすい構造=迷わずに情報へたどり着けるということ。
結果として「このサイト、使いやすいな」と感じてもらえれば、直帰率が下がったり、滞在時間が伸びたりといったユーザーシグナルの改善にもつながります。
Googleは近年、こうしたUX要素も評価に取り入れているため、サイト構造はSEOだけでなく“ユーザー満足度の土台”としても重要です。
悩んでる人 ブログからファンを作るために、SEO対策って何をしたらいいの? そもそも、SEO対策ってなぜするの? Noritoism SEO対策は一言でいうと「読者のためのブログを作る」 検索上位に表示[…]
悩んでる人 ブログには固定ページっていうものがあるんだよね? どんな時に使ったらいいのかな。 使い方が分かったら、便利そうだなー。 Noritoism 固定ページは名前の通り、その場所に固定させて情報発[…]
次のセクションでは、サイト構造を見直す前にやっておくべき「3つの準備ステップ」をご紹介していきます。
事前準備を丁寧に行うことで、実際の改善作業がぐっとスムーズになりますよ。
サイト構造を設計する前にやるべき3つの下準備

いきなり階層やリンク構成をいじり始めるのはちょっと危険です。
というのも、どんな構造が理想かは、サイトの目的や読者層によって変わってくるからです。
ここでは、サイト構造を最適化する前に必ずやっておきたい「3つの下準備」をご紹介します。
これをやっておくことで、設計ミスを防ぎ、後々の修正も最小限に抑えられます。
ターゲットユーザーと検索意図を明確にする
まず大事なのは、「誰に向けて、何を伝えたいか」をはっきりさせることです。
ここがブレていると、どんなに見た目が整った構造を作っても、ユーザーに刺さりません。
✅ チェックすべきポイント:
- 読者の年齢層・関心・目的は?
- 検索してくるときの悩み・課題は?
- 検索キーワードに対して何を届けるのがベスト?
たとえば、「ブログの始め方」をテーマにするなら、検索者の多くは「初心者でWordPressの知識ゼロ」なはず。
その場合、トップにくるべきページは「簡単な手順を紹介する記事」や「Q&A形式のまとめページ」となります。
悩んでる人 ブログ始めたいんだけど、サーバー契約とかドメイン取得って正直ちょっと怖いんだよね……。WordPressって難しそうだし、なんか途中で詰みそうな気がしてさ。 Noritoism うんうん、最[…]
既存コンテンツの整理とキーワード重複チェック
次に、今あるページの棚卸しを行います。
特に注意したいのが「同じキーワードで複数の記事を書いていないか」という点。
これを「キーワードカニバリゼーション」と呼び、検索順位を下げる原因になります。
🔍 確認方法の一例:
- サイト内検索を使って「site:noritoism.blog キーワード名」で調べる
- 表やスプレッドシートに記事タイトル・URL・狙っているキーワードを記録
- 似ているページがあれば、統合・削除・内部リンク調整を検討
サイトマップ設計図を作って全体像を把握する
構造を考えるとき、頭の中だけで組み立てるのは限界があります。
そこで役立つのがサイトマップ(構成図)です。
これは「このサイトにはどんなページがあって、どう繋がっているか」を可視化する図のこと。
紙に手書きでもOKですが、MiroやXMind、Googleスプレッドシートなどを使うと編集・共有もしやすいです。
具体的にはこんなイメージ:
トップページ
├── カテゴリA(例:ブログ運営)
│ ├── A-1:ブログ開設の手順
│ ├── A-2:WordPressの使い方
├── カテゴリB(例:SEO対策)
│ ├── B-1:内部対策
│ ├── B-2:外部対策
これを作っておくことで、「あ、こことここがつながってないな」「このカテゴリは薄いな」といった構造の偏りにも気づけます。
この3つの準備を丁寧に行えば、サイト構造の最適化も「設計」から「構築」までスムーズに進められます。
次のセクションでは、いよいよ本題。SEO効果を高めるための「6つの構造対策」をご紹介していきます!
SEOに強くなる!サイト構造の対策6選【基本から応用まで】

ここからは、SEOの効果をしっかり引き出すために実施しておきたい「サイト構造の具体的な改善ポイント」を6つご紹介します。
どれも検索順位に直結しやすい施策なので、一つずつ確実に実践してみてください。
クリック数は3回以内!シンプルな階層構造を意識する
Googleは「ユーザーが目的のページにたどり着きやすいか」を評価基準のひとつにしています。
その目安とされているのが、トップページから3クリック以内に主要なページへアクセスできること。
✅ 悪い例:
トップページ → カテゴリ → サブカテゴリ → サブサブカテゴリ → 記事
(4クリック以上かかる)
✅ 理想の例:
トップページ → カテゴリ → 記事
深すぎる階層構造は、検索エンジンにもユーザーにも不親切です。
カテゴリ設計を見直して、重要なページは浅い階層に配置するようにしましょう。
カテゴリとタグの設計ルールを決めてカニバリを防ぐ
WordPressではカテゴリとタグを自由に作れますが、無秩序に増やすと評価が分散したり、同じ内容のページが乱立するリスクがあります。
✅ カテゴリとタグの基本ルール:
| 種類 | 目的 | 運用のポイント |
|---|---|---|
| カテゴリ | 記事の“分類” | 大枠で分けて数は少なめに |
| タグ | 記事の“属性” | 関連性があるものだけ付与 |
特にタグは、「1記事に10個以上タグがついている」といった状態になっていると、タグページの乱立 → 重複コンテンツ → SEO評価の低下につながります。
タグは検索意図に応える導線になっているかを意識して運用しましょう。
パンくずリストで内部リンク強化&構造化データ対応
パンくずリストは、ユーザーが今どのページにいるのかを一目で把握できるナビゲーション。
でもそれだけじゃなく、SEO面でもかなり重要な内部リンク構造です。
Google公式でも推奨されており、構造化データ(schema.org)に対応したパンくずはリッチリザルト表示にも貢献します。
WordPressでの設置方法(例):
- 「Breadcrumb NavXT」などのプラグインを利用
- テーマによっては標準搭載されていることも多い
Hub & Spokeで回遊性アップ!戦略的な内部リンク設計
Hub(ハブ)=中心となる包括ページと、Spoke(スポーク)=詳細記事のリンク群を組み合わせる内部リンク戦略は、SEOに非常に効果的です。
たとえば「SEO対策まとめページ(Hub)」から、「内部対策」「外部対策」「キーワード選定」などの詳細記事(Spoke)へリンクを張るイメージです。
Hub & Spokeのメリット:
- ユーザーが迷わず情報にアクセスできる
- 内部リンクが自然に集まり、Hubページの評価が高まる
- 関連ページ同士が補完し合い、滞在時間・回遊率がアップ
内部リンクは、「関連があるから貼る」ではなく、構造として意図的に設計することが大切です。
XMLとHTML、両方のサイトマップでクローラビリティ向上
XMLサイトマップは検索エンジン用、HTMLサイトマップはユーザー用、それぞれの目的が違います。
- XMLサイトマップ:Googleに送信することでクロール効率を改善
- HTMLサイトマップ:訪問者が全体構造を理解しやすくなる
WordPressでの対応:
- 「XML Sitemap & Google News」や「All in One SEO」などのプラグインで自動生成可
- HTMLサイトマップは「PS Auto Sitemap」などが便利です
両方を設置することで、検索エンジンとユーザーの両方に優しい構造が実現できます。
URL正規化と重複コンテンツ対策で評価の分散を防ぐ
「同じような内容が複数のURLで存在する」状態は、Googleにとって非常に判断しづらいもの。
評価が分散し、本来上がるはずのページが上がらない原因になります。
代表的な対策:
- canonicalタグで正規URLを指定
- 不要なタグページ・日付アーカイブにはnoindex設定
- 重複ページがあれば301リダイレクトで統一
特にWordPressは「日付アーカイブ・著者アーカイブ・タグページ」など自動生成されるページが多いため、必ず確認しておきましょう。
この6つの対策を取り入れることで、検索エンジンにとっても、ユーザーにとっても“わかりやすい構造”が出来上がります。
次のセクションでは、こうして構築したサイト構造が実際に成果に結びついているか?を確認する「効果測定の方法」をご紹介します。
構造改善の効果を測定!チェックすべき指標とツール一覧
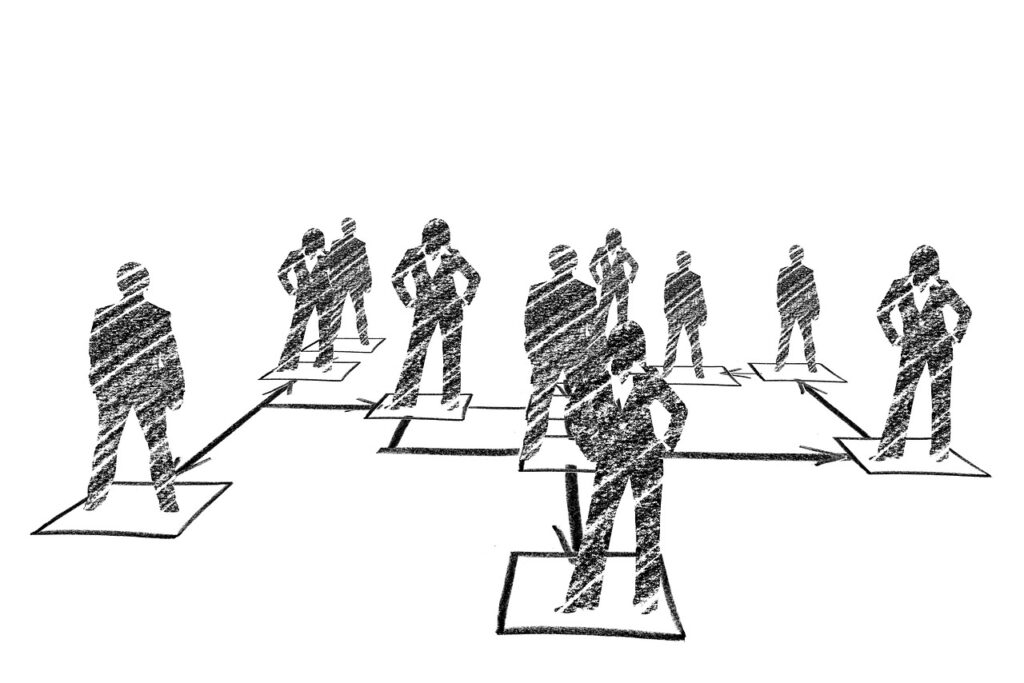
サイト構造を改善したあとは、「本当に効果が出ているのか?」をしっかりと確認することが大切です。
やみくもに変更して終わりにするのではなく、データを元に改善の成果を把握→次の打ち手へ繋げることが、継続的なSEO強化のカギになります。
ここでは、無料ツールを活用しながら確認できる、3つの代表的な測定方法をご紹介します。
Search Consoleでクロール状況とリンク構造を確認
Google Search Console(GSC)は、サイト構造の効果をチェックするうえで必須の無料ツールです。
特に次の2つの機能は、構造改善後にぜひ確認しておきたいポイントです。
✅ 確認すべき指標:
- 「クロール統計情報」:クローラーがどれだけ巡回してくれているかを確認
- 「内部リンク」レポート:どのページがリンクを多く受けているかを把握
もし「重要なページに内部リンクが少ない」と感じたら、再設計の余地あり。
内部リンク数が多いページ=Googleに「重要だ」と認識されている可能性が高いからです。
GA4で回遊率・直帰率をチェックする
構造改善は、検索エンジンだけでなくユーザー体験(UX)にも直結します。
その効果を測るには、Googleアナリティクス4(GA4)でのユーザー行動分析が役立ちます。
✅ 確認すべき指標:
- エンゲージメント率(=旧:直帰率の代替)
- 平均エンゲージメント時間(=平均滞在時間)
- ページビューが多いページの流入経路
改善前と改善後で上記の数字を比較し、「ユーザーが迷わずページを巡回できているか」「読み込みやすくなったか」といった変化をチェックしましょう。
💡構造が整理されると、回遊率アップ → 滞在時間UP → 評価向上という好循環が生まれやすくなります。
改善PDCAを回す!90日ごとの構造レビュー法
構造の改善は一度やって終わり、ではなく、定期的に見直すことが重要です。
なぜなら、コンテンツが増えてくると、自然と構造が崩れていきやすいからです。
✅ 90日ごとのチェックリスト例:
| チェック項目 | 内容 |
|---|---|
| 新しい記事の階層は適切か? | 3クリックルールを守れているか確認 |
| カテゴリ・タグは整理されているか? | 似た意味のタグが乱立していないか |
| 内部リンクの偏りが出ていないか? | 重要ページへのリンクが集まっているか |
| 低品質・不要なページはないか? | サーチコンソールの「インデックスされないページ」を確認 |
このように3ヶ月ごとの構造棚卸しを習慣にすることで、SEOの土台を安定して保ち続けることができます。
構造を改善したら、必ず効果測定までセットで行うことが、SEOの成果を最大化するコツです。
Googleのツールはすべて無料で使えるので、ぜひ習慣化してみてくださいね。
次のセクションでは、「やってしまいがちな構造設計の失敗例」とその解決法をQ&A形式で解説していきます!
やりがちな失敗とその対策Q&A|リダイレクト・タグ乱立など

サイト構造を見直す際、「良かれと思ってやったこと」が逆効果になるケースも少なくありません。
ここでは、特に多い3つの構造ミスをピックアップし、Q&A形式で原因と対処法を解説していきます。
Q1. URLを変更したらアクセスが激減…なぜ?
URLを変更すると、Googleの評価も“新しいURLに引き継がれる”ように設定する必要があります。
これをやらずに放置してしまうと、旧URLで蓄積された被リンクや評価がすべてリセットされ、検索順位が大きく下がってしまうことも。
✅ 解決策:
- WordPressの場合は「Redirection」などのプラグインを使い、旧→新URLへ301リダイレクトを設定
- Search Consoleで「インデックスされているURL」をチェックし、古いURLが残っていないかを確認
Q2. タグをたくさん付けたらSEOに良いって聞いたけど…?
タグを増やしすぎると、「同じ内容のタグページ」が量産されてしまい、重複コンテンツの温床になります。
結果としてGoogleからの評価が分散したり、インデックス除外されてしまうリスクも。
✅ 解決策:
- タグは1記事につき多くても3〜5個程度に絞る
- 同じ意味のタグ(例:「SEO」「SEO対策」「SEO講座」)は統合 or 削除を検討
- 不要なタグアーカイブページにはnoindexを設定
Q3. 内部リンクが少ない記事があるけど、どうすればいい?
検索エンジンはリンクをたどってページの関係性を理解しています。
つまり、他のページからリンクされていない記事は、評価もされにくく、クローラーにも見つけられにくい状態に。
✅ 解決策:
- 関連性のある記事から積極的に内部リンクを追加
- Hub & Spoke構造を使い、中心となるまとめページに集約
- カテゴリトップや固定ページからもリンクを設置して、“見つけてもらえる”環境を作る
| よくある疑問 | 簡単な解説 |
|---|---|
| 固定ページが増えすぎるのはOK? | OKだが、ナビゲーションに入れるかどうかを設計で決めるべき |
| カテゴリは複数設定してもいい? | 原則1記事1カテゴリがベスト(重複評価を防ぐ) |
| 「投稿」「固定」どちらを使うべき? | 情報が定期更新されるなら投稿、永続的なページは固定ページが適任 |
今回紹介したようなミスは、どれも気づきにくいけれどSEOに大きく影響する落とし穴です。
定期的な構造レビューと、正しい知識での運用を意識することで、サイト全体の評価はぐっと安定します。
次はいよいよこの記事のまとめ。
サイト構造の最適化がなぜ重要で、何をすればよいのか、もう一度整理して振り返っていきましょう!
まとめ|検索上位を狙うなら、サイト構造の最適化がカギ
SEO対策というと、つい「キーワード選定」や「記事の質」にばかり目が行きがちですが、実はその“土台”となるのがサイト構造です。
この記事では、SEOに強いサイトを作るために欠かせない構造設計のポイントを、準備段階から実装・効果測定・失敗対策まで一気通貫で解説してきました。
重要なポイントをもう一度整理すると、以下の通りです。
✅ サイト構造がSEOに効く理由は3つ
- クロール効率が上がることでインデックスされやすくなる
- 内部リンクを通じて評価が伝わりやすくなる
- 回遊性が向上し、ユーザー体験(UX)が改善される
✅ 構造を作る前にやるべき3つの下準備
- 読者の検索意図を明確にし、ゴールを設定する
- コンテンツの整理とキーワードの重複チェック
- サイトマップで全体像を可視化する
✅ SEOを強化する6つのサイト構造対策
- クリック数3回以内を意識した浅い階層設計
- カテゴリとタグの整理ルールで評価の分散を防ぐ
- パンくずリストと構造化データで検索エンジンにアピール
- Hub & Spoke構造で内部リンクを戦略的に構築
- XML/HTML両方のサイトマップでクローラーとユーザーに対応
- canonicalやnoindexで重複コンテンツを防止
✅ 改善の効果は数値で確認・分析
- Search Consoleでクロールと内部リンクの状況をチェック
- GA4で回遊率・滞在時間の変化を確認
- 90日ごとに棚卸しして構造をキレイに保つ
✅ ありがちなミスとその対策も忘れずに
- URL変更時の301リダイレクト忘れに注意
- タグの乱立や重複ページの増加はnoindexや整理で対処
- 孤立ページを減らすために内部リンクを意識的に設計
検索上位を狙うなら、まずは検索エンジンに“構造的に伝わるサイト”を作ることが不可欠です。
構造の見直しは一度やったら終わりではなく、定期的にチューニングしていくもの。
今のあなたのサイトが、検索エンジンにもユーザーにもやさしい構造になっているか、ぜひこの記事を参考にしながら点検してみてくださいね。
SEOはコンテンツだけじゃない。構造こそが、土台であり、戦略そのものです。