あれってそんなに大事なの?
実はハノンって、昔からある定番の練習教材なんだけど、
ただの基礎練じゃないんだよ。
ハノンは「どう使うか」で評価が大きく変わるんだ。
目的やレベルに合っていないと、退屈に感じちゃうのも事実。
じゃあ、ちゃんと効果を出すにはどうすればいいの?
順番とか、練習のコツとかもある?
この記事では、ハノンの基本から効果的な使い方、
年齢別のポイントまでまるっと解説してるから、ぜひ最後まで読んでみて!
◆ ハノンは意味ある?ピアノ練習における効果と限界
◆ ハノンの効果を引き出す練習方法と進め方のコツ
◆ 年齢・目的別に見るハノンの使い方と注意点
◆ ハノンだけじゃ足りない?併用したいピアノ教材3選
「ハノンってよく聞くけど、実際のところどんな練習なの?」「本当に効果あるの?」そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
ピアノを学ぶうえで“定番中の定番”ともいえるハノンですが、使い方や目的を間違えると、ただの「つまらない練習」で終わってしまうこともあります。
一方で、うまく取り入れることで、指の独立・脱力・音階感覚など、演奏の土台をしっかりと育ててくれる強力な教材でもあります。
この記事では、ハノンの基本から練習方法、年齢やレベル別の活用法、他教材との使い分けまで、網羅的に解説しています。
ピアノ初心者の方も、ブランクがある大人の方も、ぜひ参考にしてみてくださいね。
ピアノ教材「ハノン」とは?初心者にも分かる基本情報
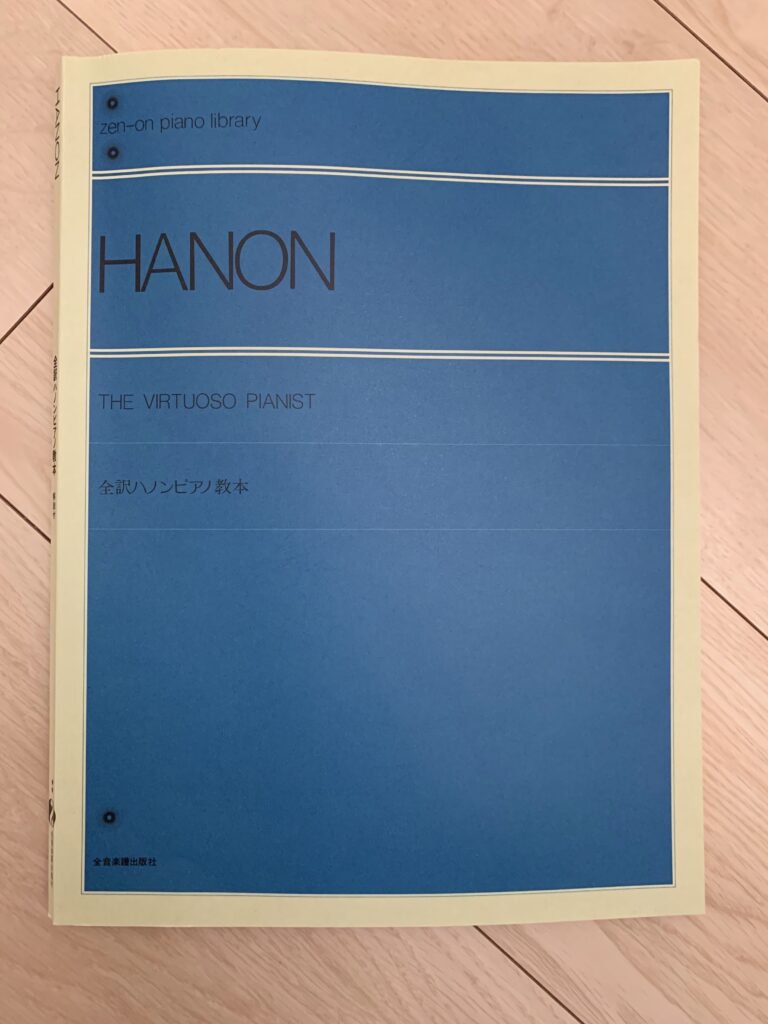
ハノンの正式名称と作曲者について
「ハノン」とは略称で、正式には
『ヴィルトゥオーゾ・ピアニストのための60の練習曲』(Le Pianiste Virtuose)といいます。
この教材を作ったのは、19世紀フランスの作曲家シャルル=ルイ・ハノン(Charles-Louis Hanon)。
彼は音楽院の教師ではなくアマチュアの音楽愛好家だったとも言われていますが、彼の練習曲は世界中のピアノ学習者に影響を与えてきました。
現在でも、クラシックからポップス・ジャズのピアニストまで幅広く使っており、“指の筋トレ”としての立ち位置を確立しています。
どんな練習ができる?ハノンの特徴と内容を解説
ハノンは、次のようなシンプルなパターン練習が60曲以上収録された教材です。
| 練習内容 | 主な目的 | 難易度 |
|---|---|---|
| 第1番〜第30番 | 指の独立・基礎的なテクニック習得 | 初級〜中級 |
| 第31番〜第43番 | 音階・アルペジオ・和音練習 | 中級〜 |
| 第44番〜第60番 | 音楽的な練習(装飾音や跳躍など) | 上級 |
特徴としては、
- 両手で同じ動きを繰り返す構成
- 運指(指番号)が明確に指定されている
- 音楽性よりも機械的な反復練習に特化
といった点が挙げられます。
そのため、「面白みに欠ける」と感じる人もいれば、「無心で指を鍛えられる」と好む人もいます。目的をはっきりさせて使うことが大切です。
なぜ定番教材なのか?今でも使われ続ける理由
ハノンがここまで長く愛用されてきた理由は、ピアノ演奏の「基礎筋力」を効率的に鍛えられるからです。
特に以下のような点で、多くの指導者や学習者に支持されています。
- 指を1本ずつしっかり動かす感覚が養える
- 脱力や手首の使い方を確認しながら練習できる
- スケールやアルペジオの導入にも最適
また、他の教材と比べてシンプルな構成なので応用しやすく、アレンジも自由自在。
「片手だけ」「リズムを変える」「スタッカートで弾く」など、自分の弱点に合わせた使い方ができるのも魅力です。
次のセクションでは、ハノンを使うメリット・デメリットを掘り下げていきます。
「意味ない」って言われることもあるハノン、実際どうなのか?気になる方はぜひ読み進めてみてくださいね。
ハノンは意味ある?ピアノ練習における効果と限界
![]()
指の独立・脱力に効果的な理由とは?
ハノンの最大の魅力は、「指を個別に動かす能力」を鍛えられることです。
ピアノは両手を使って複雑な動きをする楽器。とくに薬指・小指の動きに悩む人は少なくありません。
ハノンの反復練習は、以下のような効果があります:
- 各指を均等に使う筋力とバランス感覚が育つ
- 脱力の感覚を身につけやすい(力んだままでは速く動かせない)
- 鍵盤を正確に打鍵するフォームが安定する
とくに初心者や再開組にとっては、「手がまだピアノに慣れていない」状態なので、指の土台作りとしてかなり効果的です。
「ハノン=無意味」と言われる理由と誤解
一方で、ネット上では「ハノンは意味ない」といった声も見かけます。
これにはいくつかの誤解や前提のズレが関係しています。
| 指摘されがちな批判 | 実際のポイント |
|---|---|
| 退屈すぎて続かない | 単調なリズムと構成なので目的意識が必要 |
| 音楽性がない | ハノンは“筋トレ”教材。音楽表現とは別軸 |
| 弾けても曲が上達しない | ハノンだけで完結しようとするのはNG |
つまり、ハノンは「目的に応じた補助教材」として使うべきものであり、これだけでピアノが上手くなるわけではありません。
「音楽性を育てたい人にハノンだけ与えても、効果は感じにくい」のです。
使い方を間違えると“時間の無駄”に見えてしまうという点が、「意味ない」という評価につながってしまうのかもしれません。
ハノンが合う人・合わない人の違いを知ろう
どんな教材にも向き・不向きがありますが、ハノンも例外ではありません。
以下のような特徴を持っている人には、ハノンが向いている or 効果を実感しやすい傾向があります。
✅ ハノンが向いている人
- 指の動きにぎこちなさを感じている初心者
- 地道な反復練習が苦にならないタイプ
- 短時間でも毎日コツコツ続けられる人
- 「無音での練習」などを活かせる集中力がある人
❌ ハノンが合わない可能性がある人
- 「音楽的な表現」をすぐに学びたい人
- 退屈な練習がどうしても続かないタイプ
- 音符が読めても指が固まりやすい(脱力の理解がない)人
合わないと感じた場合も、「今の自分に必要かどうか?」を見直してみるのが大切です。
無理して取り組む必要はありませんが、“今後のステップに備えた準備”として使える場面は多い教材です。
次は、「ハノンの効果を引き出す練習方法と進め方のコツ」を解説します。
実際の順番や頻度、練習法の工夫が気になる方は、ぜひ続けてご覧ください!
ハノンの効果を引き出す練習方法と進め方のコツ

おすすめの練習順序とレベル別の進み方
ハノンは全60曲ありますが、すべてを順番通りにやる必要はありません。
実際は、自分のレベルや目的に合わせて選ぶのがポイントです。
以下に、レベル別のおすすめ進行例をまとめました:
| レベル | おすすめ練習番号 | 目的とポイント |
|---|---|---|
| 初心者(~バイエル程度) | No.1〜5 | 指の基本的な動きを安定させる |
| 初中級(ブルグミュラー前後) | No.1〜20 | 両手の連携やリズム強化にも効果的 |
| 中級(ツェルニー100番以降) | No.21〜30、31〜39 | 音階やアルペジオの導入として活用 |
| 上級(ソナタレベル以上) | 必要に応じてNo.40以降 | 弱点克服やスピード強化に特化して使う |
全部やるよりも、「今、自分に足りない部分を補う」目的で選ぶほうが効果的です。
毎日どれくらいやる?練習時間と頻度の目安
ハノンは「短時間・高頻度」が効果を発揮しやすい練習です。
おすすめの取り組み方は以下のとおりです:
- 初心者の場合:1日10〜15分(1〜2曲に絞る)
- 中級者以上:ウォーミングアップとして5〜10分程度
- 忙しい日でも1回は通す習慣を作ることが重要
注意したいのは、「長時間ダラダラ続けない」こと。
目的のない反復は集中力も下がり、フォームの崩れや無意識の力みを招く可能性があります。
✔ タイマーを使って区切る
✔ 目的を決めてから練習する(例:今日はテンポ安定重視)
この2つを意識するだけでも、効果の出方が大きく変わります。
テンポ・リズム・片手練習で効果を最大化する方法
ハノンをただ「速く弾く」だけでは意味がありません。
むしろ、以下のようなバリエーション練習を取り入れることで、ぐんと効果が上がります。
✅ 練習の幅を広げる工夫
- テンポ変化:
ゆっくり→中速→速め と段階を踏むことで、指のコントロール力が高まります。 - リズム変化:
例:♪♩|♩♪|♪♪♩|♩♪♪ のように不規則に
→ 均等な打鍵だけでなく、表現力の下地にもつながります。 - 片手だけで弾く:
特に利き手じゃない側(左手が多い)を単独で強化するのがおすすめ。
→ バランスの取れた演奏につながります。 - アクセント付け:
例:1拍目だけ強めに弾く、3音目だけスタッカートで弾く など
→ 指の独立性がグッと増します。
このように、「ただ弾くだけ」で終わらせず、自分なりに変化をつける工夫が、ハノンの本当の価値を引き出します。
次は、「年齢・目的別に見るハノンの使い方と注意点」についてご紹介します。
子どもに使っていいの?大人の再開組はどう取り入れたらいい?そんな疑問にお答えしますので、ぜひ引き続きチェックしてくださいね!
年齢・目的別に見るハノンの使い方と注意点

子どもにハノンを使う際のポイント
子どものピアノ学習にハノンを取り入れる際は、「習慣化」よりも「楽しさ」や「達成感」を大切にすることがポイントです。
✔ 向いている年齢の目安
- 小学校中学年以上(7〜8歳〜)
指の力がある程度ついてきてからがおすすめです。
✔ 取り入れ方の工夫
- 1日1パターンだけを繰り返す
- テンポより「丁寧さ」を重視
- リズム練習やリズムカードと組み合わせて遊び感覚にする
子どもにとって、ハノンの反復練習は「退屈」に感じがちです。
そのため、単調にならない工夫や、成功体験を積ませる構成がカギとなります。
また、「指の独立」よりも“鍵盤に触れる時間を増やす”という目的で取り入れるのが現実的です。
大人の初心者や再開組におすすめの使い方
大人のピアノ学習者、特に初めてピアノを学ぶ人や久しぶりに再開する人にとって、ハノンは「基礎感覚のリセット」に非常に有効です。
✔ こんな方におすすめ
- 音符は読めるけど、指が思うように動かない
- 演奏中にミスタッチが増えてしまう
- 左手が極端に苦手
✔ 効果的な活用法
- 1回5分〜10分、ウォーミングアップに取り入れる
- 指番号をしっかり確認して、力を抜いて練習する
- 録音して自分のリズムや打鍵の安定性をチェックする
大人の場合、集中力と理解力は高いため、「意識的なトレーニング」に向いています。
ただし、痛みや疲労を感じる場合は要注意。無理せず、短時間でも継続できる形が理想です。
中級~上級者がハノンを活かすためのアレンジ例
ある程度ピアノを弾けるようになると、「ハノンはもう必要ないのでは?」と感じる方も多いかもしれません。
ですが、ハノンは“基礎を再構築したい時期”にも力を発揮する教材です。
✔ こんなときに再活用が有効
- 速い曲を弾くと指がもつれる
- スケールやアルペジオが曖昧になってきた
- 表現よりも「正確な打鍵」を見直したい
✔ 上級者向けアレンジ練習例
| 工夫内容 | 具体的な方法 | 目的 |
|---|---|---|
| アーティキュレーション強化 | スタッカート+レガートで交互に弾く | 表現力の幅を広げる |
| 変拍子練習 | 5拍子や7拍子で区切って演奏する | 複雑な拍感への対応力 |
| アクセント位置変更 | 3音ごと・4音ごとにアクセントをつける | リズム感の養成 |
このように、「定型を崩して再構築する」という使い方をすれば、ハノンは上級者にとっても価値ある教材になります。
次は、「ハノンだけじゃ足りない?併用したいピアノ教材3選」へと続きます。
基礎を固めながら音楽的な成長も目指したい方は、ぜひそちらもあわせてご覧ください。
ハノンだけじゃ足りない?併用したいピアノ教材3選

ツェルニーやバーナムとの違いと役割分担
ハノンは「指の独立」や「脱力」に特化した運動系トレーニング教材ですが、演奏力を総合的に伸ばすには他の要素もカバーする教材が必要です。
そこで登場するのが、ツェルニーやバーナムといったエチュード(練習曲)教材です。
| 教材名 | 特徴 | ハノンとの違い |
|---|---|---|
| ツェルニー | 曲形式でテクニックを習得する練習曲 | 音楽性と技術の両立に向いている |
| バーナム | 子ども向けの短くやさしい練習曲集 | 動きに意味づけがされていて楽しい |
| ハノン | パターン練習で反復強化 | 音楽性より指の運動能力重視 |
つまり、ハノン=筋トレ、ツェルニー=実戦、バーナム=感覚づくりと役割を分けるとイメージしやすいです。
ハノンで培った指の基礎力を、ツェルニーやバーナムで「曲に落とし込んでいく」という使い方が効果的です。
ブルグミュラーとの併用で表現力も鍛えよう
「音楽的な演奏ができるようになりたい」「情感を込めて弾きたい」
そんな方にはブルグミュラー25の練習曲との併用がおすすめです。
ブルグミュラーは、以下のような特徴を持っています:
- 短くも完成度の高い楽曲構成
- タイトル付きでイメージがわきやすい
- 強弱・表情記号が豊富に使われている
ハノンで鍛えた指の動きがスムーズになったら、今度は“どう弾くか”を学ぶフェーズへ。
この段階でブルグミュラーを取り入れると、以下のような効果が期待できます。
- 表現力の向上(歌うように弾く感覚)
- 音色のコントロール(強弱やタッチの意識)
- ストーリー性のある演奏力の育成
ハノンだけでは得られない「音楽的な体験」を、ブルグミュラーがしっかり補ってくれます。
目的別|スケール・テクニックを伸ばす教材の選び方
もう一歩進んで、特定の目的に合わせて教材を選びたい方に向けて、以下のような目的別おすすめ教材もご紹介します。
| 目的 | おすすめ教材 | 特徴 |
|---|---|---|
| 音階(スケール)を整えたい | 全調スケール&アルペジオ集(市販) | 調性ごとの感覚が身につく |
| 曲にすぐ応用したい | ツェルニー30番・40番 | 課題別に練習曲が構成されている |
| 総合的に基礎力を高めたい | クラーマー=ビューローやモシュコフスキ | 中級以降におすすめの実戦型エチュード |
目的がはっきりしているときは、「何のためにハノン以外をやるのか?」を明確にして教材を選ぶことが大切です。
無理に多くの教材を同時にこなす必要はありません。
1〜2冊をうまく組み合わせることで、ハノンの効果をより実感できるようになります。
まとめ|ハノンを意味ある練習に変えるには?
ハノンは「ただの反復練習」「つまらない基礎練」というイメージを持たれがちですが、使い方次第でピアノ上達に大きく貢献する教材です。この記事では、その理由や効果的な活用法について、以下のポイントを押さえて解説してきました。
✔ ハノンの基礎知識と役割
- 正式名は「ヴィルトゥオーゾ・ピアニストのための60の練習曲」
- 指の独立・脱力・打鍵の安定など、テクニックの土台づくりに最適
- パターン練習で構成され、反復による習得を重視
✔ ハノンのメリット・デメリット
- 効果:指のコントロール力強化・リズム安定・無駄な力みの改善
- 限界:音楽性や表現力の習得には不向き、飽きやすい
- 「合う人・合わない人」を見極めて使うことが大切
✔ 練習を効果的にするコツ
- 目的に合わせて番号を選ぶ(全部やる必要なし)
- 練習時間は短くてもOK。毎日コツコツが大事
- テンポやリズムの変化、片手練習など工夫して飽きずに続ける
✔ 年齢・レベル別の使い分け
- 子ども:遊び要素やリズム練習と組み合わせて導入
- 大人初心者・再開組:基礎の再構築・フォーム確認に有効
- 上級者:表現力やスピードを引き上げるアレンジ活用がカギ
✔ ハノン+他教材の組み合わせが最強
- ツェルニー=実戦的な演奏技術の習得
- ブルグミュラー=表現力・音楽性を育てる
- スケール集やモシュコフスキなど、目的別の補完教材も効果的
ピアノ上達は“正しい練習の積み重ね”がすべてです。
ハノンを「意味ある練習」にするためには、目的を持って取り組むこと、そして自分に合った形にアレンジして使うことが何より大切。
無理なく・楽しく・確実に、ハノンをピアノ生活の味方につけていきましょう!
ハノン以外の効率的な練習法もご紹介しています。
悩んでる人 ピアノって練習が欠かせないよね。 どんな練習をしたら1番効果的なのかな? Noritoism ただ闇雲にピアノを弾き続ければいいわけじゃなくて、 正しい工夫でかなり効果的な練習が期待できるよ[…]
練習方が身に付いたら、コードの知識を深掘りしていきましょう。
悩んでる人 コードっていっぱいあるけど、どれも同じように見えて、正直よくわかんないんだよね。 トニックとかサブドミナントとか…名前は聞いたことあるけど、違いとか使い方っているの? Noritoism うん[…]
この記事を書いた人|Noritoism 伊藤 貴雅
ピアニスト・作曲家として活動しながら、「音楽で生きる道をひらく」をテーマに、
ブログ・BGM制作・収益化の実践情報を発信中。
▶︎ 筆者プロフィールはこちら








